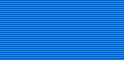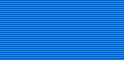| |
専門大学は高度職業人を育成するため、産業界の様々なニーズに応える必要がある。人材需給のミスマッチをなくし、多様化しているニーズを取り入れた教育を行うために、各学校に理事会と並んで、産業界の声が直接入る産業評議員会(仮称)を設置することとする。 |
| 3.評価−第3者機関による客観的評価・認定 |
| |
専門大学は第3者機関による客観的な評価及び認定を受けるものとする。評価項目は就職率、資格・検定取得率、採用された企業での処遇等の育成人材に関するアウトプット項目を始め、教育カリキュラム、学生サービス、さらに財務内容等を評価の対象とする。評価基準については、社会から高度な専門職業教育を行っていると評価される内容が必要であり、諸外国の国際的な標準との比較検討のうえ設定することとする。 |
| 4.課程 |
| |
(1) |
社会人のリカレントを容易にする
専門大学においては、社会人向けの履修形態として、比較的短期間で修得可能な特定テーマごとに履修成果を認定し、累積加算により単位修了を認める。またカリキュラム編成についても、受講者の必要とするテーマに応じて科目を組み合わせるモジュール方式を可能にすれば、正規課程の履修に算入する道が開かれる。各学校がそうした科目を開設するだけではなく、多くの「専門大学」が連携して総合的で多様なコースを提供するコンソーシアム方式も併せて考えられるべきである。また社会人の編入学を受け入れるに当たっては、職歴の評価が考慮されるべきである。
|
| |
(2) |
通信課程の設置
専門大学にはIT技術の活用等による通信課程を設置する。 |
| 5.修了及び単位 |
| |
修了に必要な単位数は152単位が望まれる。修業年限は3年又は4年とする。この中には実習、インターンシップを必修として含む。ただし専攻分野によってその単位数には幅を持たせる。 |
| 6.称号 |
| |
専門大学卒業者に対する称号は「プロフェッショナル・バチュラー(PB)」とする。 |
| 7.教員−更新制として教育力評価を明確にする |
| |
専門大学の教員制度は、教育力評価を明確にするため更新制度、任期制度を導入する。教員資格は「特定の分野について、特に優れた知識、技術、技能、経験を有し、職業教育の人材育成に適性を有すると認められる者」とする。 |
|
・「専門大学に関する答申」の取りまとめ |
専門大学推進委員会に改称されてからは、河村達夫文部科学副大臣への趣旨説明や、文部科学省専修学校教育振興室との意見交換を実施し、課題などを確認するとともに、専門大学の創設に向けた対応を協議して「専門大学に関する答申」を取りまとめ、平成15年3月の常任理事会で会長に提出し、理事会並びに総会で説明を行いました。
なお、「専門大学に関する答申」は次のとおりです。 |
専門大学に関する答申
専門大学推進委員会では平成15年1月14日に開催された第5回委員会での審議により、専門大学に関する議論をまとめ、鎌谷秀男全国専門学校協会会長に答申として提出することとなった。ここに当日の議論をまとめ、この間の資料である平成14年7月4日の全国専門学校協会定例総会で承認された「専門大学創設趣旨」と定例総会で設置が承認された専門大学推進委員会の審議経過を添付して答申とするものである(注:「専門大学創設趣旨」と審議経過は省略)。 |
■高等教育システムに対する価値観の変化 |
| |
文部科学省の平成14年度学校基本調査によると、専門学校は学校数2,969校、学生数は66万人である。短期大学は学校数541校、学生数は26万7千人となっている。入学者数は専門学校32万7千人、短期大学12万1千人、高等教育機関への進学率では専門学校21.7%、短期大学8.1%となっている。また、新規高等学校卒業者の進学者数では専門学校23万7千人で18.0%、短期大学11万人で8.4%となっている。新規高卒者の進学率は昭和63年に専門学校が短期大学を上回り、以来差が開いている。18歳人口は平成4年をピークに少子化が続いているが、10年前の平成4年度の学生数を見ると、専門学校は69万1千人、短期大学は52万5千人であった。この10年間で、高等教育システム、学校選択における「伝統的」な価値観は、明らかに大きな変化を示している。平成14年、高校生にとって専門学校は、就職という進路を抜き大学に次ぐ「第二の進路」となった。高校生は現実に「大学か、専門か。」という選択をしているのである。ところが、私立学校経常費助成費補助金に象徴されるように、社会的にその認識はまだ希薄であり「伝統的」な高等教育システムへの価値観はあまり変わっていない。特に、高校の進路指導担当者や保護者には「伝統的」な学校選択における価値観が未だに強く残っており、錯覚したまま現実の姿は正確に伝わっていない。 |
■社会の要請と現教育体系のギャップの拡大 |
| |
今日、フリーターは200万人とも言われ、若者の就職難が恒常化し、転職が一般化する中で、即戦力となる専門知識や技術・技能が必要とされるようになってきた。平成14年度における専門学校の就職率は76.7%、大学は56.9%、短期大学は60.3%である。そして大学・短期大学・高等専門学校を卒業して専門学校に入学した学生は2万6千人となっており、これは専門学校入学者の8%を占めている。この調査は、平成11年度から始まり当初は2万人であったから、ここ数年で急増している。また、大学等に在籍しながら夜間等に専門学校に通学して資格取得、技術・技能を習得するダブルスクール学生も依然として多い。戦後、我が国は、技術立国として高度経済成長の道を歩んで来たが、昨今、学校教育における職業教育、職業に就くための技術・技能教育はおざなりにされてきたのではないだろうか。ところが、若者は社会の要請と現教育体系のギャップが拡大していることに気が付いて行動を起こしているのである。 |
■社会に適応する新しい高度職業教育体系の構築 |
| |
21世紀を迎え、我が国の社会・経済は高度化、多様化し、グローバル化が一層進展する中で、まさに今、高等教育の充実を目指す構造改革が求められている。
中央教育審議会大学分科会では、専門職大学院制度の創設を答申し、本年4月から施行される。めまぐるしい技術革新や国際競争、長引く不況に対するには、企業内教育だけでは限界がある。制度の創設には必然性がある。しかしながら、専門職大学院が養成できる職種にも人数にも限界がある。
主要国の国際競争ランキングを毎年発表しているスイスのIMD(国際経営開発研究所)によると、大学教育の評価部門では、国際競争力の観点から見た日本の大学教育の充実度ランキングは2002年においても49カ国中最下位であった。
中央教育審議会大学分科会では、平成14年7月、「今後の高等教育の展望及び高等教育政策について(グランドデザイン)案」を提示している。その中で各高等教育機関が、研究重視・教養教育重視・専門職業教育重視・地域社会貢献重視等に多様化することを提案しているが、ほとんどの大学は研究重視の傾向が見られる。
今の我が国で、高度職業教育を担っているのは主に専門学校であるが、制度的には専修学校専門課程として位置付けられており、高等教育機関として独立した学校制度ではない。また、1年制も4年制も同じ専門学校という名称でくくられており、設置者の問題を含めて高等教育機関として位置付ける、明確な制度の改正が必要である。 |
■「専門大学」制度の創設 |
| |
高等職業教育機関として社会的にも、高校生や保護者・高校進路担当者等から見ても、間違った選択とならないよう明確な制度の創設が必要である。そのことにより、我が国は高等職業教育機関が重要であり必要であることをはっきりと国民に示すことになり、あらゆる教育段階で職業観を育成した上で職業教育、技術・技能教育が強調されることになる。そして、このことが日本の社会全体を活性化するためにも必要なことである。
高等教育機関として、高度職業人育成を担う「専門大学」制度の創設が求められている。 |